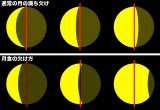スカイツリーの入場券が取れました。
かなり混雑しているという話を聞いていたので「半年先まで売切れ、みたいな感じかな?」と思っていたら、東京に行く日にちょうど空きがありました。
さて、いざ取ろうとしたら、む、難しすぎる・・・
スカイツリーのウェブサイトから「ネット予約についてはこちら」をクリックすると、そこは条件分岐の嵐。
「入場日は7月10日以前か?」「個人か団体か?」という分岐がダラダラと1ページに書かれていて、「自分が何に該当するのか、全部読まないとわからない」という素敵仕様です。これ考えたヒトは、「自販機のボタンを100回連打しないと購入できない刑」でいいと思うよ。
苦労して全文を理解し、「Webチケット」をクリックすると、今度はチケットぴあが管理する別のページに飛ばされます。そこでも微妙に異なる文言の条件分岐が・・・。まあ、内容は同じなんでしょうけど「同じ」かどうかは全文読まないと分からないよね。
これ作ったヒトは「新明解国語辞典の第3版と第4版の違いを手で書き出す刑」にしてほしい。
更に、チケット購入にはスカイツリー用のアカウントを作る必要があります。殆どの人は一生に一回しか行かないだろうに、なんでわざわざアカウント作る必要があるんだろう・・・
文句を言っても仕方ないので、アカウントを作成してクレジットで決済。すぐに予約完了メールが送られてきました。この辺の素早さは、さすがネットという感じですね。
ちなみに紙のチケットは当日まで発券できません。指定された時間内(猶予はたったの30分間)に券売機に並び、購入時に使ったクレカを差し込むとチケットが発券されるという仕組みです。
面倒くさいのは確かですが、転売防止で仕方なかったんだろうなと同情はします。
発券にはクレカが必要としたことで、ネットでの転売は殆ど防止できます。逆にオークションでスカイツリー入場券が売っていたら、まず間違いなく詐欺ですのでお気を付けください。
また、発券をわずか30分に絞っているので、現地で大量発券して転売というのも難しいでしょう。
過去の転売の手口をよく調べて対策してあるなと思います。
予約完了して一息ついたあとに最大の謎が待っていました。スカイツリーのページを見ると「発券にはクレカと購入時メールの2点が必要」という不思議な文言が書かれています。
チケット発行で「クレカ、または購入時メール」という話は聞きますが、「クレカ、かつ購入時メール」というのは聞いたことがありません。
クレジットカードの持参者が購入者であることを疑う理由はないのですから、カード以外が必要というのは不思議です。しかも、要求するものが「メールを印刷したもの、またはメール」と非常に緩い(いくらでも偽装できる)ものになっています。
一体なぜ、こんなアンバランスなルールになっているのでしょうか?
ここから先は想像ですが、「券売機のシステム上は指定時間外でもチケットが受け取れてしまう」のではないでしょうか。
「メールまたはメールのコピーを持参」などとアバウトな条件判定は人間の係員がいないと対応できないので、券売機の前では「人の目でメールを確認して、指定時間内の人だけに券売機を操作させる」というチェック体制が取られているのだろうと想像します。
もし仮に「指定時間以外の発券は一切不可能」というシステムにしてしまったら、天候などのトラブルで入場時間が乱れた時に対応ができなくなってしまいますからね。
そんなわけで、「メールで入場時間を確認」という緩いチェックをすり抜ければ、指定された時間外に券を受け取ることも可能なのかもしれません。
転売ヤーの狡猾さは目を見張るものがありますから、抜け穴ができないように頑張ってほしいものです。